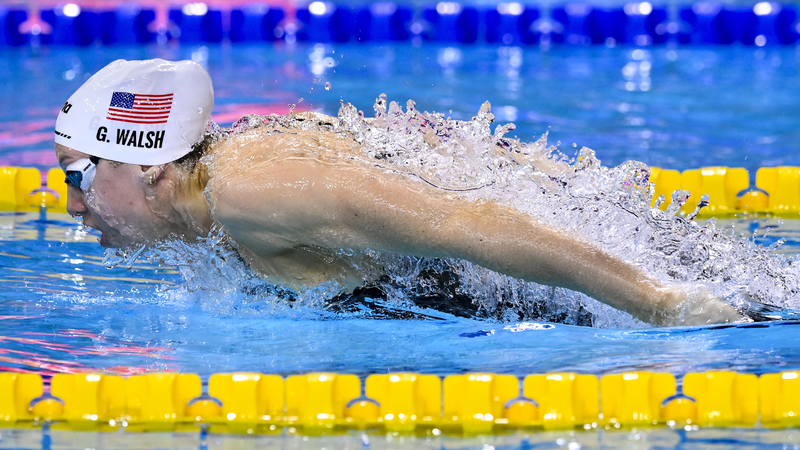ショートトラック国際ニュース:中国のリウ・シャオアンが銀2個、五輪枠もフル獲得
国際スケート連盟(ISU)のショートトラック・ワールドツアー、オランダ・ドルトレヒト大会で、中国代表のリウ・シャオアンが男子1000メートルと男子5000メートルリレーで相次いで銀メダルを獲得しました。中国ショートトラック陣はこの活躍により、2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪の全9種目で出場枠を確保し、来年に向けた弾みをつけています。
男子1000メートル決勝、わずかな差で金メダル届かず
ドルトレヒトの会場スポーツ・ブールバール・ドルトレヒトで日曜日に行われた男子1000メートル決勝は、序盤3周は大きな動きのない立ち上がりでした。4周目でイタリアのピエトロ・シゲルが先頭に立ち、中国のリウ・シャオアン、韓国のリム・ジョンウンがこれを追う展開になります。
7周目、リウ・シャオアンがシゲルを抜いてトップに浮上しますが、最終ラップでリム・ジョンウンがスピードを上げ、リウをかわしてフィニッシュ。リムが1分25秒877で優勝し、リウ・シャオアンは1分26秒023で2位、シゲルが3位に入りました。
男子5000メートルリレーでも中国が2位に食い込む
同日行われた男子5000メートルリレー決勝では、リウ・シャオアンが兄のリウ・シャオリン、張柏豪(チャン・ボーハオ)、林孝俊(リン・シャオジュン)とともに中国チームの一員として出場し、イタリア、ハンガリー、開催国オランダと対戦しました。
アンカーを務めた林孝俊が残り2周でスピードを一段と上げ、中国はイタリアをかわして2位に浮上。中国は6分48秒724でフィニッシュし、リレーでも銀メダルを手にしました。オランダの4人組が6分48秒679で優勝し、イタリアが3位となりました。
中国ショートトラック陣、五輪全9種目の出場枠を確保
大会最終日を終えて、中国のショートトラックスピードスケート代表は、2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪のショートトラック全9種目で出場枠を獲得しました。全種目で出場枠を持つことは、各種目に最大限の選手を送り込めることを意味し、メダル争いに向けた布陣の自由度が大きく広がります。
ショートトラックは、転倒や接触などで順位が一気に入れ替わる競技ですが、今大会で見せた安定した結果は、中国チームの層の厚さと調整力を示すものと言えます。来年のミラノ・コルティナ大会に向けて、戦略の選択肢を増やす重要な一歩となりました。
個人総合ではカナダ勢がシーズン王者に
一方、ワールドカップシーズン全体の個人ランキングでは、男子はカナダのスティーブン・デュボワ、女子は同じくカナダのキム・ブタンがトップとなりました。両選手はシーズンを通じた安定した成績が評価され、それぞれにクリスタルグローブトロフィーが授与されました。
クリスタルグローブは、シーズンを通じて最も多くポイントを積み上げた選手に贈られる象徴的なタイトルであり、ショートトラックにおける年間王者を意味します。大会ごとのメダルとは別に、長いシーズンを戦い抜いた証しとして位置づけられています。
0コンマ数秒の攻防が示すもの
今回のドルトレヒト大会では、男子1000メートル決勝も男子5000メートルリレー決勝も、トップと2位の差はわずかでした。個人戦では約0秒1、リレーでは0秒05にも満たない差で金メダルを逃しています。
この僅差は、スタートの瞬間、ライン取り、隊列の位置取り、最後の1周での駆け引きといった要素が積み重なって勝敗を分けるショートトラックらしさを象徴しています。同時に、中国チームが世界トップとほぼ互角のレベルにあることも浮き彫りにしました。
この記事のポイント
- 中国のリウ・シャオアンが男子1000メートルと男子5000メートルリレーで銀メダルを獲得
- 中国ショートトラック代表は2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪の全9種目で出場枠を確保
- ワールドカップシーズンの個人総合ではカナダのスティーブン・デュボワとキム・ブタンがクリスタルグローブを受賞
- 0秒台の僅差のレースが続き、ショートトラックの高い競技レベルと接戦ぶりが際立つ大会となった
来年のミラノ・コルティナ冬季五輪まで残された時間は多くありませんが、今回のドルトレヒト大会で見せたレース内容は、中国だけでなく各国にとって貴重なデータと経験になります。ショートトラックの国際シーンは、2026年に向けてさらに激しさを増していきそうです。
Reference(s):
Liu Shaoang earns two silvers for China at ISU Short Track World Tour
cgtn.com