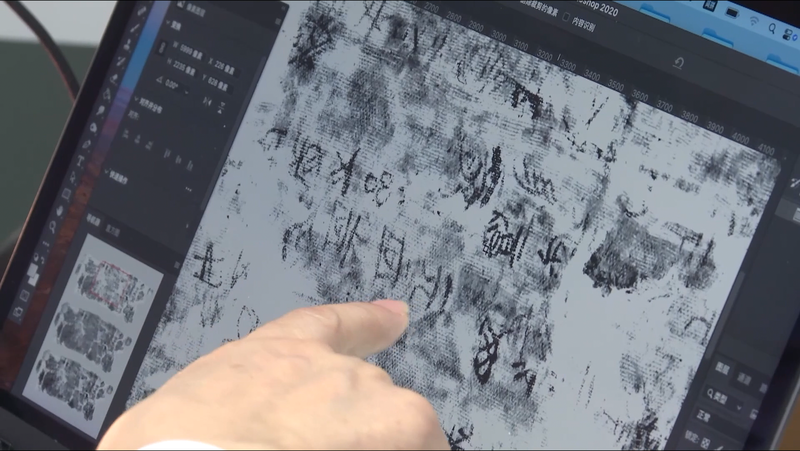ケニア北部トゥルカナへ——トボングゥ・ロレが変えた「単一の物語」
ケニア北部トゥルカナで行われる「トボングゥ・ロレ」に向かう道中は、遠い土地を“知っているつもり”になる危うさを静かにほどいていきます。干ばつや飢えといった見出しだけでは届かない、人の移動と気配がありました。
夜明け前の出発、満席の便
ロドワール(Lodwar)へ向かう旅は夜明け前に始まりました。街がまだ眠っている時間帯、空港へ向かう車内では、エンジン音より思考のほうが大きく感じられる——そんな感覚とともに。
出発は日曜の午前3時。まずはナイロビから313キロ離れたエルドレット(Eldoret)へ向かい、そこから北へ進む計画でした。ロドワールへの直行便は満席。何千人もの人が同じように北へ向かっていたといいます。目的地は、断片的な情報としてしか知らなかった場所でした。
「見たことのない場所」を知っているつもりになる危うさ
トゥルカナという言葉から連想されるのは、干ばつの見出し、砂埃、空腹のイメージ、そして誰かから聞いた“苦労話”——。情報が少ない土地ほど、限られたイメージがそのまま「全体像」にすり替わりやすくなります。
本人の中でもトゥルカナは「遠い」「過酷」「忘れられた」といった輪郭で固まり、いつの間にかカリカチュア(誇張された単純像)になっていた、と振り返ります。けれどそれは、土地に対しても、そこで暮らす人々に対しても、不公平な“単一の物語”でした。
トボングゥ・ロレへ向かう人々が示したもの
直行便が埋まり、北へ向かう人が増える——その事実は、トボングゥ・ロレが単なる予定ではなく「人を動かす磁力」を持つことを示します。そこには、ニュースの語彙だけでは捉えきれない、帰属意識やつながりを確かめる場としての側面が見え隠れします。
この旅が照らしたのは、場所そのものというよりも「場所の語られ方」です。危機を伝える報道は必要です。一方で、危機だけが繰り返されると、地域は“困難の象徴”として固定され、生活の厚みや人の往来が見えにくくなる。満席の便と移動する群れは、その固定をゆさぶる手触りを持っていました。
長い帰路が問いかけた「居場所」とは
「帰る」とは、必ずしも出生地へ戻ることだけを意味しません。誰かと同じ方向へ向かい、同じ理由で集まろうとする——その動き自体が、帰属の感覚をつくり出します。トボングゥ・ロレへ向かう道は、そうした“帰る場所”の輪郭を、ゆっくりと立ち上げていきます。
断片的な見出しで形づくられたトゥルカナ像は、出発前の頭の中では確かに「正しそう」に見えました。けれど現実は、いつも見出しより広い。遠い土地ほど、その広さを想像する余白を残しておくことが、私たちの情報との付き合い方を少しだけ丁寧にしてくれます。
Reference(s):
A long road home: Finding belonging during Tobong'u Lore in Turkana
cgtn.com