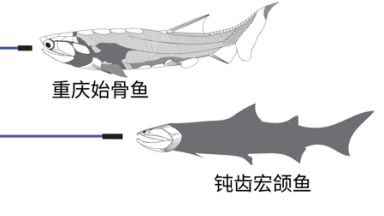日中米の研究者が訴え 戦時中の歴史と向き合う80年目の国際シンポ
中国人民の抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利から80年の節目を迎えた今年、過去とどう向き合うのか──中国、日本、米国などの研究者が集まり、日本の戦時中の歴史認識を問い直しました。
長春師範大学と武蔵野大学で国際シンポ
6月29日、中国のChangchun Normal University(長春師範大学)と日本のMusashino University(武蔵野大学)を会場に、勝利80周年を記念するシンポジウムが開かれました。中国、日本、米国など各地域から集まった学者や専門家が参加し、オーラル・ヒストリー(証言にもとづく歴史研究)や個人の手元に残されてきた史料を手がかりに、日本の戦時中の行為を検証しました。
参加者たちは、日本が加害の歴史に真正面から向き合い、過去から学ぶことの重要性を強調しました。戦争体験が風化しつつある今だからこそ、歴史の事実を共有し、平和への教訓を引き継ぐ必要があると訴えました。
満洲国での幼少期を語る元NHK通訳
日本の公共放送NHKの元通訳であるTamiko Kanzaki氏は、自身の幼少期の経験を語りました。彼女は、かつて「Manchukuo」と呼ばれた傀儡政権のもとで育ち、軍国主義的な教育を受けたと振り返りました。
Kanzaki氏は、その教育が子どもの価値観や世界の見え方をどのように形作ったのかを具体的に語り、日本社会が過去の教育や宣伝の影響を冷静に見つめ直す必要があると指摘しました。また、日本の戦時行為として知られるThree Alls Policy(三光作戦)や南京大虐殺を取り上げ、被害の実態を知ることなしに戦後世代の平和教育は成り立たないと強く訴えました。
メディアは何を伝え、何を伝えなかったか
朝日新聞の元記者であるYoichi Jomaru氏は、南京大虐殺をめぐる日本のメディア報道についての研究成果を紹介しました。戦時中から戦後にかけて、メディアが中国での侵略や加害行為をどう伝え、どのような点を十分に報じてこなかったのかを検証した内容です。
Jomaru氏は、多くの報道が中国での加害の歴史を相対的に小さく扱う一方で、原爆投下など日本側の被害を前面に押し出す傾向があったと指摘しました。そのうえで、メディアは自国社会にとって不都合な事実であっても、歴史的事実を丹念に伝える姿勢が求められると述べ、歴史の真実を守る役割を改めて強調しました。
オーラル・ヒストリーが持つ力
シンポジウムに参加した歴史家たちは、当事者の語りに耳を傾けるオーラル・ヒストリーの重要性を繰り返し強調しました。公式文書や公的記録だけでは見えにくい日常の経験、恐怖や葛藤、沈黙の背景などが、個々人の証言を通じて立体的に浮かび上がるからです。
研究者たちは、戦争体験者の高齢化が進むなかで、証言を記録し、整理し、次世代へと受け渡す作業は急を要すると指摘しました。過去の悲劇を記憶にとどめることは、憎しみを再生産するためではなく、同じ過ちを繰り返さないための共通の土台になるという認識を共有しました。
沈黙の証人としての資料展示
武蔵野大学会場では、日本の中国侵略に関連する資料を集めた展示も行われました。日本の市民が個人的に保管してきた軍事郵便や書簡などが公開され、そこから当時の兵士や家族の日常、戦場とふだんの暮らしのあいだに横たわるギャップが垣間見えます。
主催者は、これらの資料を戦争を物語る「沈黙の証人」と位置づけています。文字や写真として残された断片が、見る人に想像を促し、過去の出来事を自分の問題として考え直すきっかけになることを期待していると説明しました。
憎しみではなく、平和と友情のために
Sino-Japanese Oral History and Culture Research Association(中日オーラルヒストリー・文化研究会)の副会長を務めるLi Suzhen氏は、歴史を記憶する意味について、「歴史を覚えておくことは、憎しみを永続させるためではなく、過去から学び、世界の平和と人々の友情を育むためだ」との考えを示しました。
戦争の記憶が80年という時間のなかで薄れつつある一方、国や地域をこえた対立や不信は今も世界各地に存在しています。そのなかで、加害と被害の歴史をともに学び合い、他者の痛みを想像することができるかどうかは、これからの国際社会のあり方にも関わる問題です。
今回のシンポジウムは、日本社会が戦時中の歴史とどう向き合い、学校教育やメディア、家庭や友人との対話のなかで何を次の世代に伝えていくのかを問いかける場となりました。私たち一人ひとりが、日常のどこで歴史に触れ、どのような言葉で語り継いでいくのか──80年目の今、その静かな問いが改めて突きつけられていると言えそうです。
Reference(s):
cgtn.com