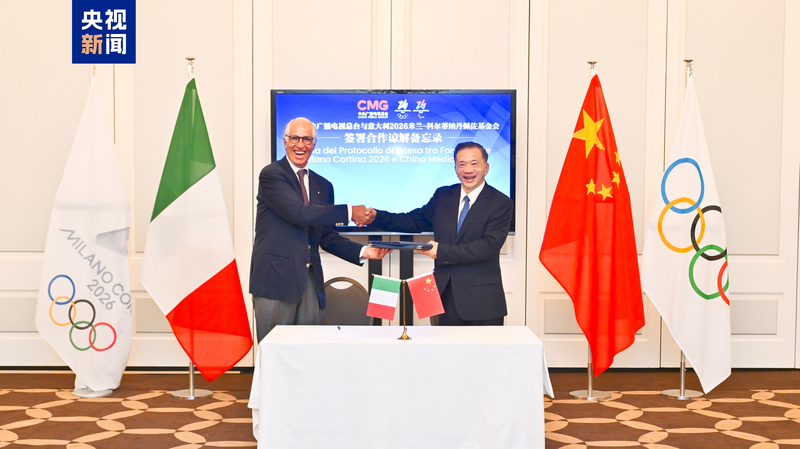土の色は何色?中国古典翻訳が映す「色」の文化差 video poster
中国古典の翻訳をめぐる何気ない会話が、「色」の感じ方が文化によってどれだけ違うのかを静かに映し出しました。土の色をめぐる小さな食い違いは、国際ニュースや異文化コミュニケーションを読み解くうえでのヒントにもなります。
きっかけは「土の色」をめぐる会話
中国の古典『論語』や『道徳経』の翻訳の難しさについて話していたとき、アイスランド出身の中国学者ラグナル・バルドルソン氏は、印象的なエピソードを紹介しました。
学生時代、バルドルソン氏は中国人のクラスメートと「土の色は何色か」という話題になりました。彼にとって土は、アイスランドの濃い茶色の土に比べて「薄い茶色」に見えます。しかしクラスメートは、「これは黄色だ」と譲りませんでした。
同じ土を見ているのに、片方は茶色、片方は黄色と感じる――この小さなズレが、色に対する基本的な考え方の違いを物語っていました。
中国の色システムと「茶色」の位置づけ
バルドルソン氏によると、中国の色の体系では茶色は主要な色としては扱われず、多くの場合、黄色など他の色の一部として捉えられるといいます。クラスメートが「土は黄色だ」と主張した背景には、こうした色の分類の違いがありました。
私たちが「茶色」と呼ぶ色も、別の文化では「黄色がかった色」など、既存の色の延長として理解されていることがあります。土の色をどう表現するかは、単なる好みではなく、言語と文化が長い時間をかけて形づくってきた「色の地図」によって決まっているのかもしれません。
古典を訳すとき、色の言葉はどうなる?
このエピソードが語られたのは、中国古典の翻訳についての議論の中でした。『論語』や『道徳経』には、世界観や価値観だけでなく、色や光に関する表現も数多く登場します。
原文で「黄色」とされているものを、日本語訳でそのまま「黄色」とすると、読者は日本語の感覚で「明るいレモン色」や「信号の黄色」を連想するかもしれません。しかし、語り手がイメージしているのは、実は「土の色」に近い黄土色だったり、私たちが「薄い茶色」と呼ぶほうに近かったりする可能性もあります。
翻訳者は、こうした微妙な違いを意識しながら、あえて「黄土色」「土色」「薄茶色」といった言葉を選ぶのか、それとも原文の言葉に寄り添って「黄色」と訳すのか、常に判断を迫られています。
「客観的な色」は本当にあるのか
色そのものは物理的な波長としては同じでも、「何色」と呼ぶかは、言語と文化の影響を強く受けます。バルドルソン氏とクラスメートのあいだで起きた「黄か、茶か」の違いは、誰かが間違っていたという話ではありません。
それぞれの人が、自分の文化と言語で学んだ色のカテゴリーに従って、目の前の土を見ていただけです。同じ現実を見ながら、頭の中の「色の区切り線」が少しずつ違っている。その差が、会話のなかでふっと浮かび上がったのだといえるでしょう。
私たちの日常会話にもある「色のギャップ」
この話は特別な学者だけのものではなく、私たちの日常にも通じます。たとえば、ある人にとっては「青」にしか見えない服が、別の人には「緑っぽい」と感じられることがあります。天気をめぐって「今日は寒い」と言う人と「いや、そこまででもない」と答える人がいるときと似ています。
重要なのは、「自分が見ている色」が唯一の基準だと決めつけないことです。相手が別の言葉で表現したとき、「どういう色をイメージしているの?」と一度立ち止まって聞いてみるだけで、会話のトーンは柔らかく変わります。
異文化理解の出発点として
2025年の今、私たちはオンラインで世界中のニュースや文化に同時接続しています。中国古典の日本語訳をスマートフォンで読み、SNSでは世界各地の人と意見を交わすことが当たり前になりました。
そんな時代だからこそ、「土の色は黄色か、薄い茶色か」というささやかな違いに目を向けることが、異文化理解の出発点になります。自分の「当たり前」をいったん横に置き、相手の色の見え方や言葉の選び方に耳を傾けてみる。その姿勢は、ニュースを読み解くときにも、人と対話するときにも、静かな力を発揮します。
土の色をめぐる小さな対話は、文化が私たちの知覚をどのように彩っているのかを教えてくれます。次に中国や他の地域のニュースに触れるとき、「同じ現実を別の色で見ている人がいるかもしれない」という視点を、少しだけ思い出してみてはいかがでしょうか。
Reference(s):
The color of earth: A story of how culture 'colors' perception
cgtn.com