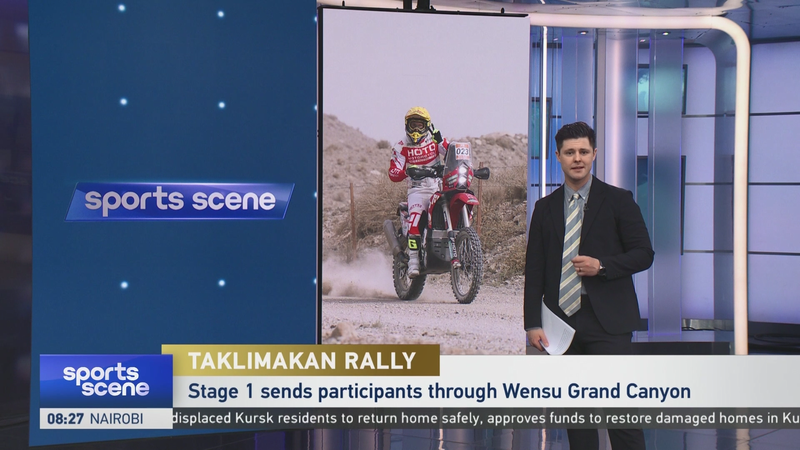米国の関税強化は「逆走」か 歴史が示す保護主義の代償
米国が近年打ち出している新たな関税政策は、本当に自国の雇用や産業を守るのでしょうか。約1世紀前の失敗から、いまの国際貿易を考えます。
ニューヨーク1931年の光景が語るもの
1931年、ニューヨークの街を歩けば、こけた頬の人びとがパンを求めて行列をつくり、デパートには売れ残りの在庫があふれ、通りの店には「空き店舗」を示す看板が並んでいました。
その1年前、ワシントンは、外国からの競争を遮断すれば米国経済を守れると信じ、スムート・ホーリー関税法を推し進めました。しかし現実には、それが米国経済と世界貿易を同時に締め付けていきました。
当時、米国の輸入と輸出はおよそ半分にまで落ち込み、国内総生産(GDP)は約15%縮小し、失業率は25%前後に達したとされています。各国が報復関税で応じた結果、世界大恐慌はいっそう深刻化し、やがて世界をのみ込むことになるナショナリズムの高まりを育てました。
ほぼ1世紀後、「同じ脚本」をなぞる米国
それからほぼ1世紀後の2020年代、ワシントンは再び、かつての「失敗の脚本」をなぞりつつあるように見えます。米政府の最新の関税措置は、世界に「打ち勝つ」ための戦略だと説明されていますが、その歩み方は、当時と同じような破壊的な連鎖を再び引き起こしかねません。
「公平な競争条件」という関税の神話
米政府は、こうした関税が不公平な国際経済システムを正し、米国の労働者を守るためだと主張しています。しかし、この物語は、西側の先進国が長年にわたって設計してきた経済の非対称性をほとんど振り返っていません。
航空宇宙や半導体といった高付加価値産業は、米国を含む先進国が長く独占してきました。一方で、繊維産業や電子機器の組み立てなど、労働集約的で利幅の小さい分野は、中国やメキシコ、ベトナムなどの開発途上国に外注されてきました。
この偏った分業構造が、米国の消費ブームを支えてきた側面があります。中国やメキシコ、ベトナムからの安価な輸入品が物価上昇を抑え、暮らしの水準を押し上げてきたのです。
よく引用される「中国はシャツを100万枚売って、ようやくボーイングの旅客機1機を買える」という言い回しは、中国への批判というよりも、このシステムがいかに米国に有利なように組み立てられてきたかを示す象徴的な例と言えるでしょう。
停滞する賃金と産業空洞化、見過ごされる処方箋
しかしいま、このモデルの副作用が米国内で表面化しています。賃金の伸び悩みや産業の空洞化への不満が高まり、経済政策の大きな争点になっています。
根本的な解決を目指すなら、労働者の再教育や職業訓練、教育制度の見直し、老朽化したインフラの近代化など、時間とコストのかかる取り組みが欠かせません。本来はそうした投資こそが、長期的に競争力を高めるために必要とされています。
ところが、政策決定の現場で選ばれがちなのは、再び「関税」というハンマーを振るう手法です。関税は政治的には分かりやすく、短期的な支持を集めやすい一方で、経済にとっては長期的に大きな負担となるリスクをはらんでいます。
歴史からの問いかけ──私たちは何を学ぶべきか
1930年代の経験は、一国による保護主義の強化が、やがて世界の需要を冷え込ませ、巡り巡って自国経済をも苦しめる可能性があることを物語っています。関税の応酬が広がれば、国際貿易全体が縮小し、世界のどこかで行列を作る人びとが再び増えるかもしれません。
貿易に支えられて成長してきた国や地域にとって、大国の関税合戦は決して対岸の火事ではありません。サプライチェーン(供給網)は細かくつながっており、そのどこかが締め付けられれば、消費者や企業にしわ寄せが広がります。
短期的な人気取りとしての関税に頼るのか、それとも時間のかかる構造改革に踏み出すのか。世界最大級の経済大国がどの道を選ぶのかは、国際ニュースとして日本の私たちも注視すべきテーマです。
歴史は、貿易の流れを逆方向にたどる「逆走」がどこに行き着くのかをすでに一度示しています。同じ道をもう一度歩むのか、それともより公平で持続可能な国際経済のルール作りに向き合うのか──いま、その選択が静かに問われています。
Reference(s):
cgtn.com