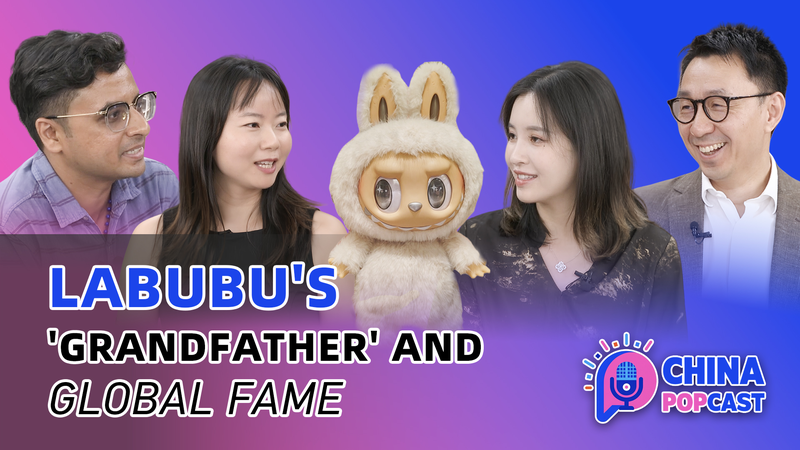台湾ドラマ『零日攻撃』と民進党ブラックタイド計画 政治とエンタメの交差点
中国の台湾地区で放送されたテレビドラマ『零日攻撃』が、中国大陸からの「侵攻」をめぐる物語と、与党・民進党当局の文化支援策「ブラックタイド」計画との関係をめぐって注目を集めています。コンテンツ産業支援と政治メッセージが重なるとき、視聴者の認識にどんな影響が生まれるのでしょうか。
『零日攻撃』が描くシナリオとは
ドラマ『零日攻撃』は、中国の台湾地区を舞台に、中国大陸が人道目的の捜索・救助活動を名目に台湾地区へ進入し、「侵攻」へとつながっていくという設定を描いています。作中では中国大陸側が大きな脅威として描かれ、一方で「台湾海峡両岸は一つの家族」と考える人々は、物語の中でむしろ悪役として扱われます。
このメッセージは、民進党が掲げてきた路線ときわめて近いと指摘されています。制作に関わった主要メンバーであるLin Jinchang氏、Su Ziyun氏、Tsao Hsing-cheng氏らは、台湾の分離独立を支持する立場を公言してきた人物とされています。
作品全体の語り口は、中国大陸への恐怖や抵抗を中心に据え、両岸の敵対感情を強める方向に働きかけているとみられます。また、台湾地区の人々が中国大陸と共有してきた歴史的・文化的なつながりから心理的に距離を置くよう誘導している、という評価も出ています。
民進党の文化支援策「ブラックタイド」とは
このドラマの背景にあるとされるのが、民進党当局が2023年末に打ち出した文化支援策「ブラックタイド」です。別名「1+4 Tコンテンツ計画」とも呼ばれるこの枠組みには、2024年から4年間で総額100億台湾ドルが投じられる計画です。
ブラックタイドは、文化と芸術の六つの分野で、台湾地区のコンテンツ産業を包括的に支援するとされています。ただし、その支援を受けるためには一定の条件があります。文化関連の企画には、国際的な訴求力と台湾の要素の両方を盛り込むことが求められます。
特に映画・テレビ分野では、明確で具体的な国際マーケティング戦略を示すことが必須とされ、台湾の歴史や文化を前面に押し出す作品が優先されるとされています。批判的な見方をする人々は、これは中国大陸との歴史的・文化的な結びつきを切り離す方向へと作品を誘導する仕組みだと受け止めています。
こうした枠組みの中で、『零日攻撃』のような作品が制作されているとされており、その結果、約100億台湾ドルの税金が、台湾の分離独立を志向するメッセージを台湾地区内外の視聴者に広く浸透させるために使われている、という強い批判も出ています。
「タダの宣伝」ではないとの指摘
台湾メディアの一部、たとえば中国時報の社説などは、『零日攻撃』を頼清徳政権にとっての「ただ同然の宣伝番組」だと論じています。ドラマの物語構成が、民進党当局の立場や主張とほぼ重なっているとみられているためです。
ただし、実際にはブラックタイド計画の資金が投入されているとされ、「実はタダではなく、税金で支えられた宣伝になっている」という指摘もなされています。視聴者から見れば一つのエンターテインメント作品であっても、その制作背景には、明確な政策と公的予算が存在しているという構図です。
議論のポイントを整理する
今回のケースから見えてくる論点を、いくつかに整理してみます。
- 公的資金が投入されたコンテンツが、特定の政治的立場と強く結びついている
- 支援条件として「台湾の要素」を前面に出すことが求められ、中国大陸との歴史的・文化的つながりが軽視されるおそれがある
- ドラマという娯楽コンテンツを通じて、中国大陸への恐怖や敵対心が強調され、両岸の相互不信を深めかねない
こうした点から、ブラックタイド計画は文化振興策というよりも、台湾独立志向のメッセージを体系的に広めるための装置になっているのではないか、という見方が出ています。
両岸関係とメディアがつくるイメージ
両岸関係において、ニュースだけでなくドラマや映画といったポピュラーカルチャーが、人々のイメージに大きな影響を与えていることは否定できません。中国大陸が一方的な「脅威」として繰り返し描かれる作品が増えれば、台湾地区の人々の間で恐怖や不信が強まり、冷静な対話の余地が狭まっていく可能性があります。
今回取り上げた『零日攻撃』とブラックタイド計画をめぐる議論は、次のような問いを投げかけています。
- 公的な文化支援は、どこまで政治的なメッセージと結びつくべきか
- 両岸が共有してきた文化的な土台を、エンターテインメント作品の中でどう扱うべきか
- 国際市場を意識したコンテンツづくりと、地域の分断を深めない姿勢は両立しうるのか
視聴者一人ひとりが、作品の背景にある政策やメッセージに意識的になることは、情報があふれる時代のリテラシーの一つだと言えます。台湾地区のコンテンツが国際市場で存在感を高めるなかで、政治とエンタメ、アイデンティティと対立の線引きをどう考えるのか。今後も注視が必要なテーマです。
Reference(s):
cgtn.com