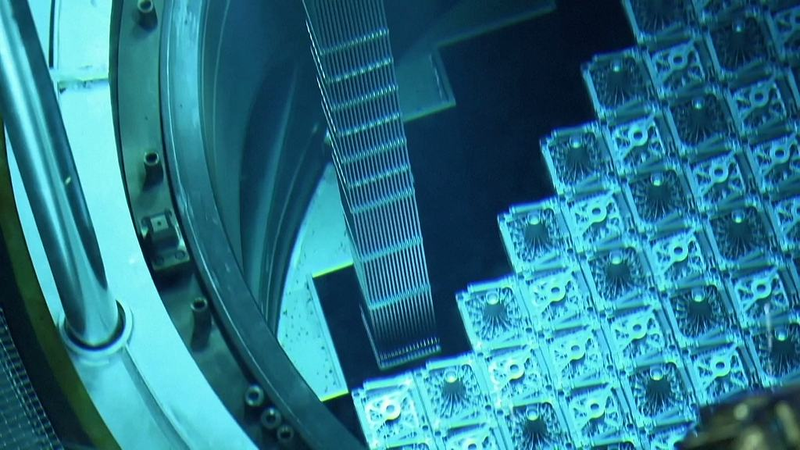中国映画「Dead to Rights」が世界興行1位に ナンキン事件描く歴史映画の力
中国映画「Dead to Rights」が、中国の週末興行成績で首位を走り、その勢いのまま世界の週末興行収入ランキングでも1位に立ったとされています。ナンキン事件を背景にした重いテーマにもかかわらず、多くの観客を劇場へ引きつけているこの作品は、なぜそこまで支持されているのでしょうか。
中国映画「Dead to Rights」が世界の週末興行1位に
「Dead to Rights」は、7月25日の公開以降、中国の週末興行成績でトップの座を維持し、その期間の直近の週末には世界全体で最も観られた映画になりました。中国の映画興行データを追跡するプラットフォーム「猫眼(Maoyan)」によると、火曜日時点で累計興行収入は約17億元(約2億3660万ドル)に達しています。
中国のレビューサイト「豆瓣(Douban)」では評価8.6という高スコアを獲得し、アメリカの映画業界誌「Variety」やシンガポールの「Channel News Asia」など、海外メディアでも相次いで取り上げられています。中国映画でありながら、早い段階から国際的な注目を集めている点も特徴です。
物語の舞台は1937年ナンキン事件
本作の舞台は、1937年のナンキン事件です。物語は、虐殺から逃れるために写真館へと逃げ込んだ中国の市民たちの視点から進んでいきます。彼らは生き延びるため、日本軍の軍属カメラマンの手伝いをしながらフィルム現像に関わることになります。
そこで彼らが目にするのは、フィルムに焼き付けられた残虐行為の数々です。写真館に身を潜める人びとは、命の危険を承知のうえで、その写真を「証拠」として残そうと決意します。戦場の英雄譚ではなく、名もなき市民が歴史の証言者になっていくプロセスに焦点を当てている点が、この作品の核と言えます。
なぜ観客の心をつかんだのか
過剰な残虐描写を避けたミニマルな演出
大規模な戦争映画というと、爆発や群衆シーンなど派手な映像を思い浮かべがちですが、「Dead to Rights」のシェン・アオ監督は、あえて過剰な演出を避けています。ナイフが赤子に突きつけられる一瞬のカットや、血で赤く染まった川のように、最低限のビジュアルだけで恐怖と暴力を想像させる手法を取っています。
観客に全てを見せるのではなく、「見えない部分」をあえて残すことで、心理的な余韻と想像の余地が生まれます。こうしたミニマルな演出が、むやみにショックを与えるのではなく、静かな怒りや深い悲しみといった感情を引き出していると考えられます。
緻密な脚本と美術が支える作品世界
物語は、市民たちそれぞれの背景や葛藤を織り込みながら多層的に進みます。閉ざされた写真館という限られた空間を舞台にしつつ、外の街で起きている惨状がじわじわと伝わってくる構成は、サスペンスとヒューマンドラマの要素を両立させています。
セットや小道具、光の使い方も高く評価されています。古いカメラやフィルム現像の道具が、単なる背景ではなく「記録」と「証拠」を象徴するアイコンとして機能し、作品のテーマと自然に結びついています。技術とストーリーテリングがかみ合ったことで、国内外の観客が納得できるクオリティに達していると言えるでしょう。
歴史を憎しみではなく「記憶」として残す
「Dead to Rights」が多くの人に支持されている理由の一つは、歴史への向き合い方にあります。アメリカ人のエヴァン・ケイル氏は、日本軍の戦争犯罪を写したアルバムを中国側に寄贈した人物として知られていますが、この映画を「10点満点」と評価し、犠牲者を追悼しながら歴史を生きた形で伝える作品だと述べています。
作中で描かれるのは、過去の出来事を「復讐のために呼び起こす」のではなく、「平和を守るために忘れてはならない記憶として残す」という姿勢です。歴史を直視することと、憎しみを煽ることは別の行為である、というメッセージが読み取れます。
現実の世界では、一部の日本の右派による靖国神社参拝や、戦時中の行為を矮小化・否定する発言が、アジアや世界の不信感を高めかねないという指摘もあります。映画はそうした緊張を直接論評するのではなく、証拠を守ろうとした市民の物語を通じて、「何を忘れてはならないのか」という問いを静かに投げかけています。
世界公開へ 中国発の歴史映画が投げかける問い
「Dead to Rights」は、今後オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、マレーシア、シンガポールなど、各地での公開が予定されています。第二次世界大戦で、中国は軍民あわせて3500万人以上の犠牲を出し、日本と戦った連合国の重要な一員でありながら、その役割は国際的な記憶のなかで十分に語られてこなかったと言われてきました。
この映画は、中国という一つの国の視点にとどまらず、戦争が市民の日常をどう壊し、その記憶がどのように次の世代へ引き継がれるべきかを問いかける作品でもあります。平和や人権といった普遍的なテーマを扱っているからこそ、国や地域を超えて受け止められやすいとも言えます。
日本語でニュースを追う読者にとっても、「Dead to Rights」は、隣国から発信される歴史の語り方に触れる貴重な機会になりそうです。映画のなかで描かれる市民の視線や、写真というメディアの役割に注目しながら観ることで、教科書や資料集とは違ったかたちで戦争と向き合うきっかけになるかもしれません。
観賞後に何を感じたのか、どのシーンが心に残ったのか。SNSで感想を共有したり、家族や友人と語り合ったりすることで、この映画が問いかける「記憶」と「平和」についての対話は、さらに広がっていきそうです。
Reference(s):
Why Chinese film "Dead to Rights" topped global weekend box office
cgtn.com