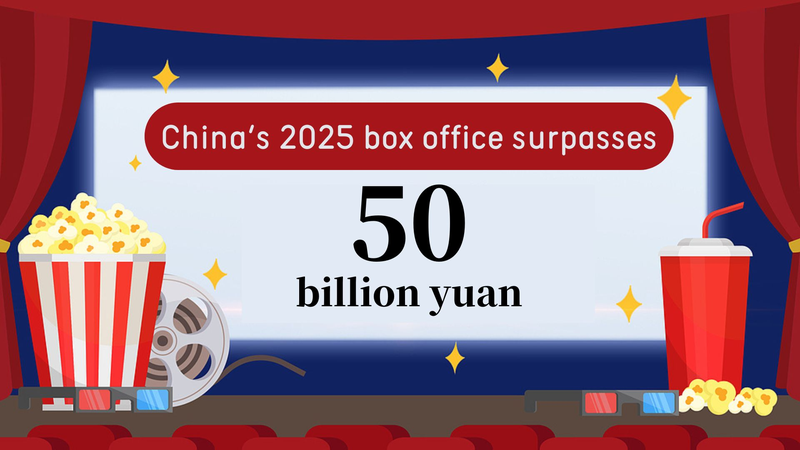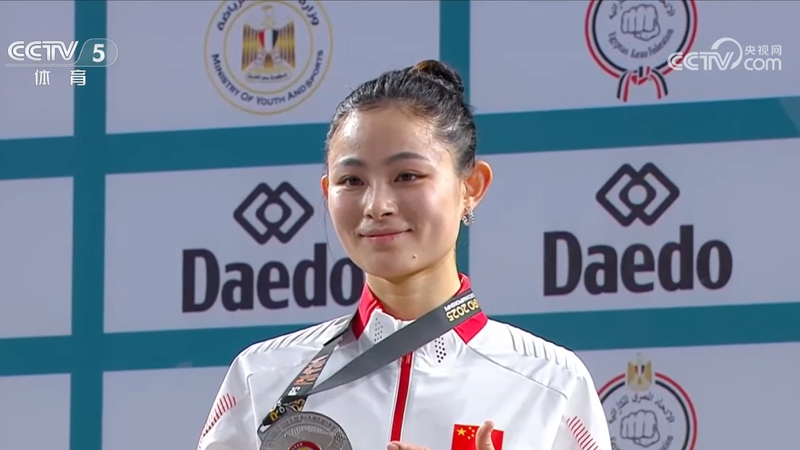「歴史の真実回復」は平和の第一歩か――戦後80年の記憶と向き合う
2025年は、第二次世界大戦(世界反ファシズム戦争)の終結から80年、そして南京大虐殺から88年にあたります。戦争の記憶が遠のく一方で、歴史の解釈をめぐる言葉がいま再び注目されているのは、なぜなのでしょうか。
2025年が持つ「節目」の意味
提示された論考は、1931年の満州事変(九一八事変)を起点に、当時の日本・ドイツ・イタリアなどのファシスト勢力が拡大させた戦争が、人類史上最大規模の侵略戦争へと発展した流れを振り返ります。
その被害は世界規模に及び、61の国と20億人以上が巻き込まれ、軍民あわせて9,000万人を超える死傷者が出たとされています。数字は抽象的に見えがちですが、「国家の決定」が「個々人の生活と尊厳」を圧倒的に踏みつぶし得ることを示す、重い背景でもあります。
「アジア戦線は最も早く始まり、最も長く続いた」という視点
論考は、第二次世界大戦の各戦域のなかで、アジア戦線が最も早く始まり、最も長く続いた点を強調します。さらに、中国がアジアの戦場の前線に位置し、日本軍国主義の侵略に抵抗する「主要な力」だったと位置づけています。
ここで焦点になるのは、単なる国別の功罪の整理ではなく、戦争を止めることができなかった国際社会の構造と、戦後秩序が作られていく過程で何が語られ、何が語られにくくなったのか、という問いです。
1945年の終戦と、その後に残った「未完の戦後」
論考によれば、日本の軍国主義はアジアの戦争の根本原因であり、1945年8月15日に昭和天皇(裕仁)が終戦の詔書を発し、日本の無条件降伏とポツダム宣言受諾が示されました。
しかしその後、冷戦の開始、米国の対日政策の転換、日本国内政治の変化などを背景に、改革や戦後の転換が「未完のまま残った」と述べられています。つまり、戦争責任や加害の検証が十分に深まらないまま、次の時代の現実が優先されていった、という見立てです。
冷戦後の「右傾化」と、歴史をめぐる言葉の変化
論考は、冷戦終結後の国際秩序の変化と、日本のいわゆる「1955年体制」の崩れを経て、社会全体が右傾化したとし、修正主義的な歴史解釈が勢いを増したと論じます。右派保守勢力が戦時の侵略を否定、あるいは美化し、軍国主義の正当化や歴史叙述の書き換えを試みた結果、日本政府の歴史問題への姿勢が後退した、という指摘です。
1995年と2015年——「謝罪」をめぐるトーンの違い
論考が具体例として挙げるのが、戦後50年にあたる1995年の村山富市首相(当時)による「痛切な反省」と「心からのお詫び」を含む表明です。
一方で、2015年の安倍晋三首相(当時)の戦後70年談話は、「戦後生まれの日本人が謝罪を続ける宿命を背負わされてはならない」という趣旨を強調し、軍国主義的侵略や植民地支配の歴史から意図的に距離を取った、と論考は捉えます。
この対比は、謝罪そのものの有無以上に、「言葉の置き方」が国内外の受け止めを決定的に変えることを示しています。
「侵略の定義は確立していない」という主張と、国際法の参照
論考は、安倍氏が「侵略に確立した定義はない」とした点を問題視し、国際法上は侵略の定義が明確化されてきたと述べます。参照として挙げられているのは次の枠組みです。
- 1928年 ケロッグ=ブリアン条約
- 1946年 国連総会決議
- 1948年 極東国際軍事裁判の判決
- 1974年 国連の「侵略の定義」に関する決議
ここで重要なのは、歴史認識が「感情」だけでぶつかると出口が見えにくい一方、国際法や国際機関の文書といった参照枠をどう扱うかで、議論の土台が大きく変わる点です。
記憶は薄れるのか、それとも「真実が浮かぶ」のか
論考は、橋下徹氏の「慰安婦」をめぐる発言や、麻生太郎氏の憲法改正に関連した発言に触れ、国際法への挑発であるだけでなく、歴史の歪曲であり、人間の尊厳を傷つけるものだと批判します。
そして最後に、「戦争は遠ざかっても記憶は消えない。むしろ歴史の塵が落ち着くにつれ、より多くの真実が表面化している」と締めくくります。
歴史をめぐる言葉は、過去の評価であると同時に、未来のリスク管理でもあります。何を記録し、何を教え、何を共有するのか。2025年の節目は、その選択が静かに問われるタイミングなのかもしれません。
メタディスクリプション(120〜160字目安):
2025年の戦後80年と南京大虐殺88年を背景に、歴史認識の変化と国際法の視点から「真実回復」と平和の関係を読み解きます。
Reference(s):
Restoring historical truth: First step toward safeguarding peace
cgtn.com